X線の観測に限りませんが,
天体の観測は一般的に,
1. 電磁波(光)などで天体からの信号を受信し検出する(検出)
2. 信号を処理して有意なデータを取得する(整約)
3. 取得したデータを画像やグラフなどに表現する(表示)
の3段階に大きくわけられます.
またしばしば,
4. 観測結果を解釈し天体現象のモデルを作る(解釈・モデル)
などの段階が続きます.
|
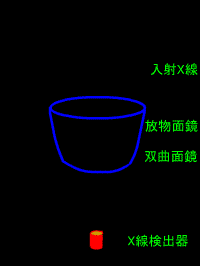 |
検出
天体からやってくる微弱な電磁波(光,X線,電波など)を,
観測装置で捉えることを,(信号の)検出(detection)といいます.
業界用語では,(信号が)受かったともいいます.
透過性の高いX線にはふつうの望遠鏡や光検出器は使えません.
特別な観測装置と検出器を設計します.
|
|---|
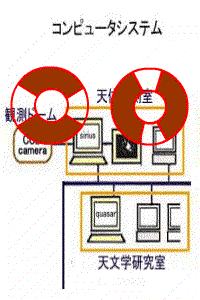 |
整約
観測して得られた生データを役に立つデータに処理する過程を,
データの整約(data reduction)と呼びます.
最初に,観測装置による器差を補正したり,
背景の余分な光を差し引いたり,
その他の不要なノイズを除去したりします.
そして目的天体の位置や明るさを精密に測定し,
生データは定量的で有効な情報になります.
検出するのは難しいX線も,デジタルデータにしてしまえば,
基本的な整約処理は可視光などの観測とそんなに変わりません.
ただしX線は一般に非常に微弱なので(X線光子が一つ一つ数えられるぐらい),
有意なデータを取得するためには十分な統計処理が必要です.
|
|---|
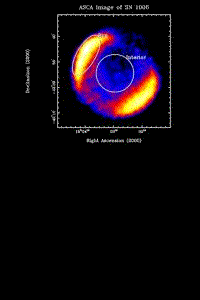 |
表示
観測の目的に応じて,取得した有意な観測データを,
画像に表したり,時間変化を示したり,スペクトル図を作ったりします.
画像に加工するときの色の着け方のような表現方法(presentation)
は,従来はあまり重要視されていませんでしたが,
観測の一つの大事な段階だと考えられます.
データの上手なプレゼンテーションは,X線でも可視光でも同じです.
|
|---|
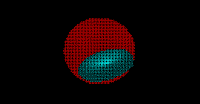 |
解釈とモデル
観測して得られたデータから,
天体のサイズや温度やガスの組成などを導くことができます.
ただし一般的には,得られるデータはそれだけでは不充分なことが多いので,
多くの場合はなんらかの仮定を立ててデータを解析(analysis)し,
妥当な結果を導きます.
さらに画像や時間変化やスペクトルなどのデータを物理的に解釈(interpretation)して,
天体の構造や変化を推測したり,隠された法則性を調べたりします.
またしばしば,枝葉末節を切り捨てて描像を単純化したモデル(model)を立て,
そこで起こっている天体現象の本質を突き止めます.
そのようなモデルが普遍性や予測性をもったときに,
そのモデルは理論(theory)と呼ばれます.
|
|---|


 Go to Submenu
Go to Submenu Go to Menu
Go to Menu