ロイ・カー@基礎物理学研究所市民講演会
(2007/12/01)
|
今年最大のビッグイベントである。
ロイ・カーの講演会に行って、握手もして、ツーショットまで取ってきた!
ロイ・カーといっても知らない人の方が圧倒的に多いだろうが、
ブラックホールの業界では、
1962年にカー解を発見したロイ・カー(Roy Patric Kerr;1934〜)は、
現在の世界では伝説的な最大のビッグネームだろう。
実際、宇宙に存在するほとんどすべてのブラックホールは、
球対称で静的なシュバルツシルト・ブラックホールではなくて、
自転しているカー・ブラックホールだと信じられているのだ。
ぼく自身は扱いの面倒なカー解は修士論文のときを含め数えるほどしか使ったことないが、
教科書などでは素知らぬ顔でカー解をよく知っているような記述をしている(笑)。
ま、とにかく、ブラックホール物理学の分野では、アインシュタインは別格として、
シュバルツシルト解を発見したカール・シュバルツシルトのつぎに
重要な歴史的人物がロイ・カーなのだ。 |
|
 |
講演の準備をするカー 1934年生まれとあったが、73には見えないしっかりした感じである。 |
|---|---|
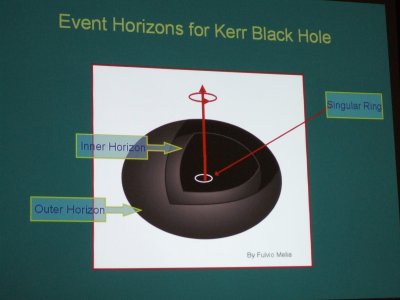 |
講演半ばの一枚 講演内容は、前半はニュートン重力から一般相対論へ至る話で、 後半はカー解の発見の細かい経緯だった。 話し方は平易だけど内容はきわめて高度で (実際、相対論プロパーの話だと、どうしてもそうなるが)、 前半の話についていけたのは、ほんのわずかだっただろう。 そこらへんは、つぎの嶺重さんがフォローしたのだろうが、 基礎物理の市民向け講演もなかなか難しいものだ。 後半、とくに1960年代初頭のカー解へ至る発見の物語は、 当事者の口が語るだけに生き生きして面白かった。 |
 |
質問に答えるカー 1時間ほど講演があり、その後、少し質問タイム。 最初は学生から、algebraically specialとはどういうことかと質問。 ストレートな質問でぼくも知りたかったが、 かなり専門的な質問なので、難しいよなぁ。 その後は3人ほど質問があったが、いやまぁ、何というか、 最初から答えられないことが明らかな質問ばかりで、 司会の佐々木さんも四苦八苦な感じ。ほんと大変だ。 ぼくも質問いっぱいしたかったけど(笑)、 この段階では少し控えめに・・・ |
 |
突撃タイムtoカー 予想通り10分ほど休憩が入ったので、 Thank you very much for your nice and impressive talk. とか何とか挨拶に行く(もちろん事前に作文していて)。 ぜんぜん控えめじゃない(爆)。 |
 |
ツーショットwithカー そしてもちろんツーショット。 休憩時間とはいえ、200人ぐらいの人がいる前で、よくやるなぁ。 |
 |
みんな一緒にwithカー 京都産業大学の学生さんたちと。 もう撮ったもん勝ちである。 |
 |
みんな一緒にwithカー こっちは京大の学生さんたちかな。 そうそう、10年後20年後にお宝になるんだよ。 |
| 本人の口から聞いた歴史的な経緯はやはり知らないことだらけで、 とくに一番勘違いしていたのは、カー=ニューマン解だった。 自転していて電荷をもっている解としてカー=ニューマン解というのがあるのだが、 ずっと以前は、カーとニューマンの共著論文があるのだと思っていた。 しばらく前に、実はそんな論文はなくて、ニューマン他という論文があることがわかり、 カー解を発展させた解としてニューマンが電荷をもった解を見つけたので、 カー=ニューマン解と呼ばれるようになったのだと思ったし、 本とかにもそう書いてしまった。しかし事実はさらに違っていて、 カー自身が自分の解に電荷を入れた解を見つける一方、 ニューマンたちも電荷をもつ解に自転を入れた解を発見したという、 それぞれ独立の発見だったらしい。 “なるほど!!” | |