講義概要/Lecture Guide
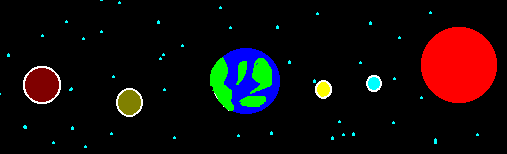
開講区分 専攻科目 区分 教員
授業科目名 地学II 開講期 前期
講義題目 天文学 曜日時限 木3
担当教官名 福江 純
講義概要
天文学と呼ばれる科学の一部門について、何を観測し、如何に解析し、何故かを識ることを直接的な目的とした概論を行う。また間接的・併設的な目標としては、
科学知識体系:知識と使い方、
科学的方法論:3段階論、
科学の最先端:ブラックホールの素顔、
科学表現論:マルチメディアコンテンツ、
科学と哲学:ここはどこ? わたしはだれ?
お気楽極楽科楽:いかに科学を楽しむか、
などについても、触れていきたい。
授業計画
1 宇宙の表現representations
1・1 数学的な表現
1・2 物理的な表現
1・3 天文学的な表現
2 宇宙の現代像modern views
2・1 宇宙誌1:天体の種類と階層構造
2・2 宇宙誌2:天体の誕生と宇宙の歴史
2・3 太陽系最前線:太陽系の構造と形成
2・4 恒星の世界:星の種類と進化
2・5 銀河の領域:銀河の分類と形成
2・6 活動天体:降着円盤の活動と宇宙ジェット
2・7 時空の構造:ブラックホールのシルエットと重力レンズ
2・8 宇宙の変転:ビッグバンと宇宙の膨張、そして未来
2・9 青い惑星:地球の誕生、地球システム、第二の地球
2・10 宇宙と生命
3 観測量と推定量observables and derivables
1 天体の位置を決める
2 地球の大きさと月の大きさを測る
3 小惑星の動きを調べる
4 惑星の自転速度、連星の公転速度、ジェットの速度
5 一等星の明るさ
6 赤色巨星の色と温度
7 超新星のエネルギー
8 ブラックホールの重さを量る
9 星間雲の密度
10 銀河・星までの距離を求める
11 太陽の寿命と地球の年齢
12 人間と星の組成
13 見えないものを測る
講義の方法・評価方法等
マルチメディアコンテンツを利用しつつ、講義を進めていく。また適宜、演習を課すことがあるので、関数電卓を持参のこと。成績は、期末試験と小テストなどで評価する。
テキスト なし
参考文献 横尾武夫他『新・宇宙を解く』恒星社厚生閣
参考文献 粟野他『宇宙スペクトル博物館<可視光編>天空からの虹色の便り』裳華房
開講区分 専攻科目 区分 教員
授業科目名 天文学Ⅰ 開講期 前期
講義題目 宇宙物理学 曜日時限 木4
担当教官名 福江 純
講義概要(授業の目的・内容)
“天体は静かで悠久不変である”というのが従来の支配的な考え方だった。しかし、森羅万象は移り変わっていくのが世の定め。この無限の宇宙の表象も常に流転し続けているのだ。とりわけ、最近の研究では、そのような激しい天体活動が注目を浴びている。
本講義では、現代の宇宙物理学を学ぶための第一歩として、重力の基本的性質、天体の形状の考察、光情報の種類と解析など、宇宙を取り扱う方法について紹介する。また時間が許せば、新しい活動的な天体現象について、マルチメディアのコンテンツなどを使って概観したい。
授業計画
Ⅰ 宇宙の力学
1 重力(『解く』)
2 地上の力学
3 スペースコロニーの力学
4 天体のまわりの力学
5 惑星の力学(『解く』)
6 連星の力学(『解く』)
7 星団の力学(『解く』)
8 銀河の力学(『解く』)
9 銀河団の力学(『解く』)
10宇宙の力学
Ⅱ 天体の形と流れ
1 静水圧平衡と状態方程式
2 地球大気の構造
3 スペースコロニーの大気
4 太陽大気の構造
5 降着円盤の鉛直構造
6 回転星の大気
7 連星の形状
8 降着トーラスの構造
9 星の内部構造
10 銀河円盤の鉛直構造
Ⅲ 天体からの光
1 電磁波スペクトル
2 輻射場の基礎
3 黒体輻射のスペクトル
4 熱制動放射
5 シンクロトロン放射
6 逆コンプトン散乱
7 原子スペクトル
8 分子スペクトル
9 中性水素 21 cm 線
10 電子・陽電子対消滅線
講義の方法・評価方法等
プリントを配って、その重点を説明し、適宜、演習を課す(関数電卓を持参のこと)。成績は、演習課題の提出・レポートなどで評価をする。
テキスト なし
参考文献 横尾武夫他『新・宇宙を解く』恒星社厚生閣
参考文献 柴田一成他『活動する宇宙』裳華房
開講区分 専攻科目 区分 教員
授業科目名 天文学Ⅱ 開講期 前期
講義題目 宇宙物理学 曜日時限 金2
担当教官名 福江 純
講義概要(授業の目的・内容)
本講義では、以下のテーマについて、年替わりメニューでお送りしている。
(1)「星の構造と進化」:現代天体物理学の基礎である<星>について、重力不安定による形成、水素核融合による安定した主系列星時代、そして白色矮星・中性子星・ブラックホールにいたる進化を解説する。
(2)「活動銀河とブラックホール」:クェーサーをはじめとする活動的な銀河を題材にしつつ、観測技術や輻射過程など、現代天文学の基礎的概念と最先端の描像を記述する。授業中に配布するプリントには数式がテンコ盛りだが、できるだけ図や言葉を通して物理的な概念を説明したい。
(3)「降着円盤と宇宙ジェット」:最近の研究では、激しい天体活動の背後に「降着円盤」と呼ばれる天体が存在していることがわかってきだ。現代天文学で解明されつつある活動的な天体現象について述べる。
授業計画
(宇宙流体力学)
Ⅰ 粒子と流体
Ⅱ ガス天体の構造
Ⅲ 回転の効果
Ⅳ ダイナミクス
Ⅴ 自己重力ガス球
(星の構造と進化)
0 はじめに 星とは
Ⅰ 星の形成-主系列星まで
Ⅱ 星の構造-主系列星
Ⅲ 星の進化-巨星への道
Ⅳ 星の終末-コンパクト星
Ⅴ 星の復活-終末星の活動
(活動銀河とブラックホール)
Ⅰ 活動銀河とは
Ⅱ 観測
Ⅲ 理論
Ⅳ 観測的証拠:出力
Ⅴ ふたたび:活動銀河とは
-宇宙観の変革
(降着円盤と宇宙ジェット)
Ⅰ 天体活動
Ⅱ 太陽活動
Ⅲ 銀河活動
Ⅳ 降着円盤
Ⅴ 宇宙ジェット
講義の方法・評価方法等
プリントを配って、その重点を説明し、適宜、演習を課す(関数電卓を持参のこと)。成績は、演習課題の提出・レポートなどで評価をする。
テキスト なし
参考文献 横尾武夫他『新・宇宙を解く』恒星社厚生閣
参考文献 柴田一成他『活動する宇宙』裳華房
開講場所区分 教員養成課程
授業科目名 地学構造論Ⅰ 開講区分 専攻科目
講義題目 活動する宇宙 開講期 前期
担当教官名 福江 純 月曜日 4時限
講義概要(授業の目的・内容)
“天体は静かで悠久不変である”というのが従来の支配的な考え方だった。しかし、真の姿は違う。森羅万象は移り変わっていくのが世の定め。この無限の宇宙の表象も常に流転し続けているのだ。とりわけ、最近の研究では、そのような激しい天体活動の背後に「降着円盤」と呼ばれる天体が存在していることがわかってきだ。本講義では、現代天文学で解明されつつある活動的な天体現象について述べる。
授業計画
Ⅰ 天体活動
Ⅱ 太陽活動
Ⅲ 銀河活動
Ⅳ 降着円盤
Ⅴ 宇宙ジェット
講義の方法・評価方法等
プリントを配って、その重点を説明し、適宜、演習を課す(関数電卓を持参のこと)。成績は、演習課題の提出・フリーディスカッション・レポートなどで評価をする。
テキスト なし
参考文献 柴田一成他『活動する宇宙』裳華房
理科教育内容学
地学分野では、マルチメディアコンテンツを利用しながら、
(1)ここはどこ、わたしはだれ-自然界における自分の位置付け
(2)ものごとを観るということ-自然界の中の光と色
(3),(4),(5)受講者による模擬講義および最新宇宙像の紹介
(6)どこからきて、どこへいくのか-地球誌と地球システム
などを予定している。
 福江ホームページへもどる
福江ホームページへもどる
 天文学研究室へもどる
天文学研究室へもどる
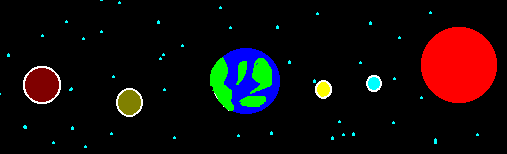
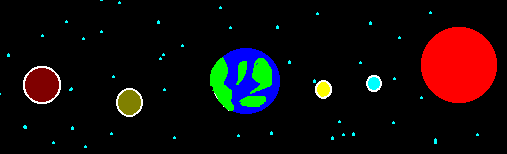
 福江ホームページへもどる
福江ホームページへもどる 天文学研究室へもどる
天文学研究室へもどる